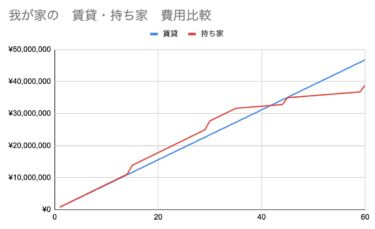家を建てるというのは人生で何度も経験することではなく、ほとんどの人にとって一生に一度の大きな決断です。
そのため、「ああしておけばよかった」「もっと調べればよかった」と後悔の気持ちが湧いてくることもあります。
今回は、家の断熱性能について「もう少し高性能な家にすればよかった」と悩んでいる方のお問い合わせを目にしました。
このような後悔とどう向き合えばよいのか、一緒に考えていきましょう。
お問い合わせの要点
- 現在、家を建築中
- 断熱等級5と6の間の性能だが、より高性能(等級6・7)の家も選べたのではないかと後悔
- 建築会社は信頼性や対応力を重視して選び、間取りには満足
- しかし、家の性能について十分に調査しなかったことを後悔している
- 冬の寒さに不安を感じ、後悔の気持ちを消化できずにいる
なぜ後悔してしまうのか?家づくりの難しさ
家づくりにおいて、「100%完璧な選択」をするのはとても難しいものです。
なぜなら、人の欲求には際限がなく、決断のタイミングでは分からなかったことが後から見えてくるからです。
例えば…
- もっと収納スペースを増やせばよかった
- もう少し広いリビングにすればよかった
- キッチンの設備をワンランク上げればよかった
このような後悔は、ほとんどの人が一度は感じるものです。
特に「家の性能」は、目に見えにくい部分なので、住んでみて初めて気づくこともあります。
ですが、ここで一度冷静になりましょう。
本当に後悔するほどの差があるのか? それとも、情報を見たことで心理的に不安を感じているだけなのか?
断熱等級の差はどのくらい影響するのか?
今回のケースでは、断熱等級が5と6の間ということですが、そもそも「断熱等級」の違いはどの程度の影響を及ぼすのでしょうか?
断熱等級とは?
断熱等級は、家の断熱性能を示す指標で、日本の住宅性能表示制度の一環として設定されています。
2022年に新たに等級6・7が導入され、より高性能な断熱住宅が求められるようになりました。
等級ごとの違い(おおまかな目安)
| 断熱等級 | 断熱性能の目安(UA値) | 省エネ性能 |
|---|---|---|
| 等級4(従来の最高等級) | 0.87以下 | 2000年基準 |
| 等級5 | 0.66以下 | 2020年基準(ZEH基準) |
| 等級6 | 0.46以下 | 先進的省エネ住宅 |
| 等級7 | 0.26以下 | 最高レベルの省エネ |
等級が上がるほど、断熱性能が高くなり、冷暖房の効率が良くなります。
しかし、日本の温暖な地域(太平洋側など)では、等級5~6程度でも十分な快適性を得られることが多いのです。
つまり、等級6や7が必ずしも必要だったのか? という点を冷静に考えることが大切です。
「今の家」で快適に暮らすためにできること
「断熱性能がもう少し高ければ…」と後悔するよりも、今の家でできる快適な住まいづくりを考えることが前向きな解決策になります。
1. 窓の断熱対策をする
家の断熱性の多くは「窓の性能」で決まります。
今からでもできる対策として、以下の方法があります。
✅ 内窓(インナーサッシ)を追加する → 断熱性が大幅アップ
✅ 断熱カーテン・ハニカムスクリーンを活用 → 窓からの冷気を防ぐ

2. 床・壁の冷気対策
冬の寒さは、床や壁からの冷気でも感じることが多いです。
✅ カーペットやラグを敷く → 体感温度を2~3℃アップ
✅ 断熱シートを窓際や壁に設置 → 体感温度アップ
3. 暖房の使い方を工夫する
高断熱住宅でなくても、暖房の効率を上げる方法はあります。
✅ エアコンとサーキュレーターを併用 → 温かい空気を部屋全体に循環
✅ 床暖房やこたつを活用 → 体感温度が上がり、暖房の設定温度を下げられる
決断した自分を認めることも大切
後悔の気持ちは誰にでもありますが、「その時にできる最良の選択をした」という事実を受け入れることも大切です。
例えば、カメラやスマホを買うとき、「最新モデルを待てばよかった…」と思うことはありませんか?
でも、考え続けている間に、大切な思い出を撮り逃してしまうかもしれませんよね。
家づくりも同じです。
「次に建てるときはこうしよう」と前向きに捉えることで、今の家でもより快適に暮らす工夫ができるようになります。
まとめ|後悔を未来への学びに変えよう!
- 後悔は誰にでもあるが、100%完璧な家は存在しない
- 断熱等級5~6なら、温暖な地域では十分な性能
- 今からできる断熱対策で快適な暮らしを実現できる
- 決断した自分を認め、未来の学びに活かすことが大切
「もっとこうすればよかった…」という気持ちは、次の行動につなげることで価値が生まれます。
まずは、今の家でできる工夫を考えながら、これからの暮らしをより快適にしていきましょう!